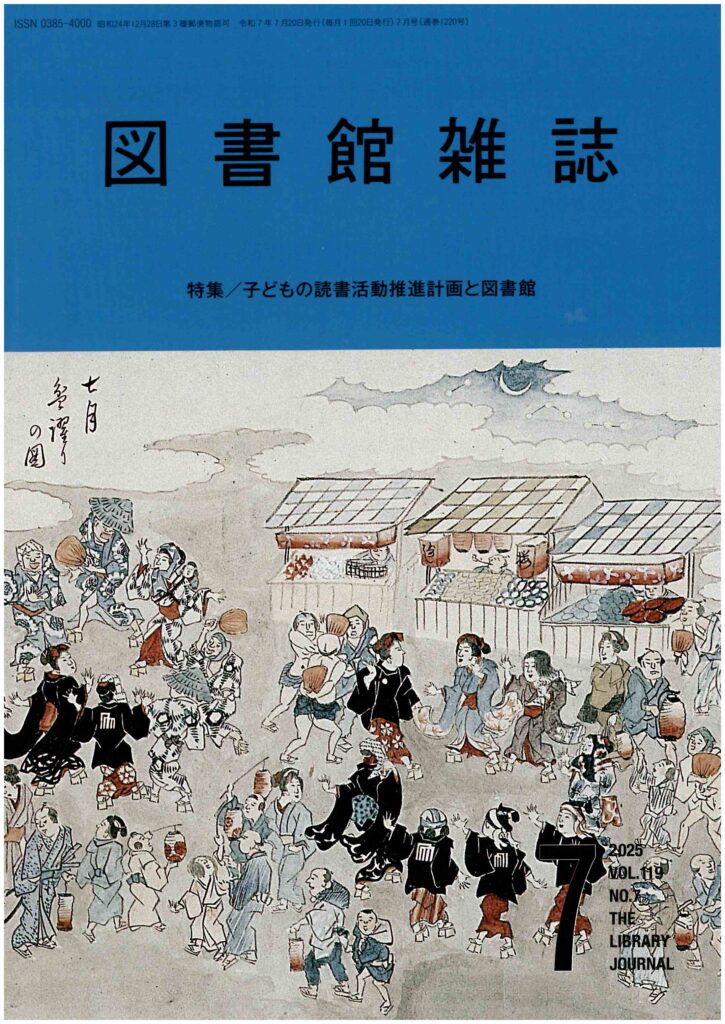
【特集】子どもの読書活動推進計画と図書館
・特集にあたって(図書館雑誌編集委員会)
・子ども読書活動推進計画と児童サービスを考える(島 弘)
・第五次「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」を読む-自治体における計画策定の意義と学校図書館との連携-(有山裕美子)
・第三次横浜市民読書活動推進計画の策定について(今川万理)
・子ども読書活動推進計画の策定への専門職のかかわり-実効性と確実な効果につながる計画に向けて-(宮澤優子)
・「第三次刈羽村子ども読書活動推進計画」の策定経過と特徴-「生きる力と豊かな感性 読書で育む かりわっ子」の育成に向けて(田中貴裕)
○IFLA-UNESCO学校図書館宣言2025(庭井史絵・岩崎れい訳,日本図書館協会)
2025年7月号 Vol.119 No.7
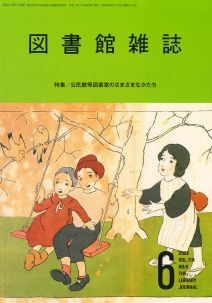
【特集】「公民館等図書室のさまざまなかたち」
・特集にあたって(図書館雑誌編集委員会)
・公民館図書室の現代的意義-「本棚の手前」から広がる可能性(青山鉄兵)
・地域に根付いた「読書の場」として-小規模図書室をフルに活かす大網白里(佐久間直美)
・東日本大震災を乗り越えて-女川つながる図書館の今(佐藤克己)
・構想から20年。待望の図書館が開館。-公民館図書室~つなぎ図書館(利府町図書館)~「リフノス」利府町図書館(今野宏)
・チャンスをつかめ!-公民館図書室から公共図書館へ(藤山明子)
・国立市における公民館図書室独自の役割-本を通して人のつながりをつくる(辻口朋香)
・沖縄県立図書館の公民館図書室への支援について(神里茉里)
2025年6月号 Vol.119 No.6
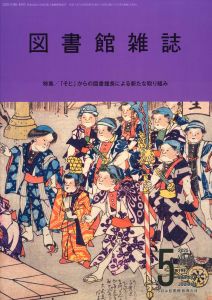
【特集】「そと」からの図書館長による新たな取り組み
・特集にあたって(図書館雑誌編集委員会)
・図書館の可能性を引き出すマネジメント-一般行政職からみた館長職とは(嶋田学)
・「行政職で培った経験・感覚」は強い武器になる-行政職の図書館長として(山本章弘)
・わたしたちはどこへ向かうのか-大学から県立長野図書館に飛び込んで実践したこと(森いづみ)
・「小さなまちの奇跡の図書館」館長論-NPO法人本と人とをつなぐ「そらまめの会」の18年の軌跡(下吹越かおる)
・指定管理館の館長になって(藤坂康司)
・原点を問い続ける-今どこにいて、どこからきて、これからどこへ向かうのか(志賀アリカ)
2025年5月号 Vol.119 No.5
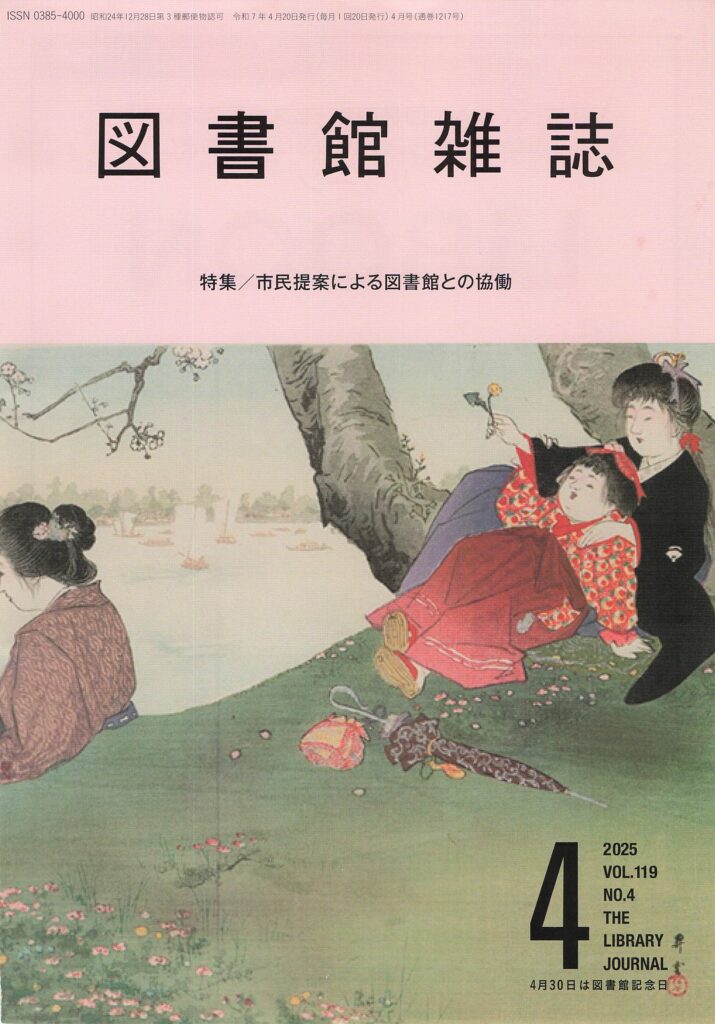
【特集】「市民提案による図書館との協働」
・市民提案型の協働事業制度の現状と課題-図書館や社会教育施設における展開のために
・もみわ広場でつながる喜びー市民提案の協働事業に参加した7年間
・しょうないREX 18年の軌跡-地域と共に歩んだ道のりー
・市民提案型まちづくり支援事業「市民のための図書館を.市民が考える講座」-守山市立図書館友の会の取り組みを通してー
・高齢者施設への読書支援-市民の「読みたい」を叶えるために
・『田原のむかし話を伝える』-紙芝居とデジタルデータによる渥美線電車機銃掃射の前日物語-
・自分が欲しかった時間を いま必要な人へ
・本を通して地域を知るー図書館と協働事業から見る地域存続への新しい側面
2025年4月号 Vol.119 No.4
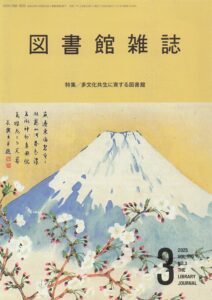
【特集】「多文化共生に資する図書館」
・図書館の多文化サービスと向き合って-多文化サービス委員会の活動(浜口美由紀)
・むすびめの会(図書館と多様な文化・言語的背景をもつ人々をむすぶ会)-多様性があり公正で包摂的な共生社会の実現をめざす人的ネットワーク(阿部治子)
・愛知県図書館の多文化サービス(新川裕美)
・大久保図書館の多文化サービスについて-人と人とがつながりあえる図書館をめざして(米田雅朗)
・埼玉県立図書館の多文化サービス普及に向けた取り組み(福士明日香)
・IFLA多文化社会図書館サービス分科会と日本の多文化サービス(平田泰子)
・多文化共生に資する学校図書館の施策と実践(野口武悟)
2025年3月号 Vol.119 No.3
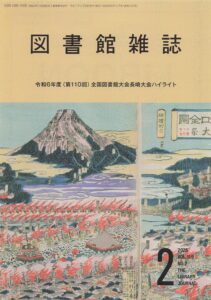
〇「令和6年度(第110回)全国図書館大会長崎大会ハイライト」
・2024年11月30日(土)・12月1日(日)に長崎県長崎市で開催、11月30日から2025年1月10日の間オンライン配信された全国図書館大会の概要を、全体会・分科会ごとに報告するほか、大会参加者の感想を掲載。
2025年2月号 Vol.119 No.2
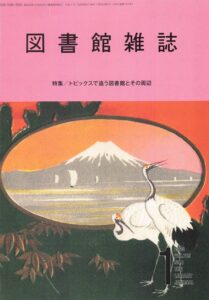
○新春エッセー「図書館の発見について」(アンナ・ツィマ)
【特集】「トピックスで追う図書館とその周辺」
・個人情報保護法の変遷と図書館-令和2年及び3年改正を踏まえて(新保史生)
・調査基盤としてのレファレンス・サービス-科学・医療分野のレファレンス・サービスに対する社会的ニーズ(渡辺真希子)
・「みなサーチ」1年の歩みと活用のすすめ(本田麻衣子)
・1000万冊のストーリー-東京大学附属図書館における蔵書1000万冊達成を記念した広報事業について(近藤真智子)
・足立区立中央図書館の未返却図書資料対策プランについて(高橋冬子)
・行政支援サービスの軌跡(徳安由希)
・書店支援で市民と図書館が連携(伊端隆康)
・千葉市図書館情報ネットワーク協議会のご紹介-館種を超えた地域の図書館ネットワーク(吉野知義)
2025年1月号 Vol.119 No.1
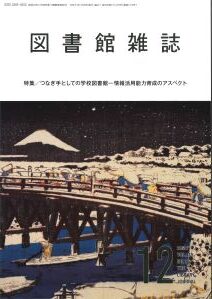
【特集】「つなぎ手としての学校図書館-情報活用能力育成のアスペクト」
・場としての図書館の実空間から情報空間に橋を架ける-デジタル資源カードという提案(岡本真)
・教科・単元別の教材用図書リストのデータベース化(浅石卓真・矢田竣太郎)
・地域資料の収集と学校図書館(小熊真奈美)
・学校図書館施設計画の留意点-学校図書館の設計をめぐる対話をどうするか(笠井尚)
・ひとが集まる学校図書館のつくりかた―本を読むだけの場所ではもったいないやん!児童生徒が集い活気にあふれる学校図書館を学校の’ど真ん中’に!(野村太郎)
○ブリスベンで開催された「IFLA情報未来サミット」(長塚隆)
2024年12月号 Vol.118.No.12

【特集】「シン・デジタル・ライブラリー-オープンサイエンス時代の大学図書館」
・2030年の大学図書館としての「デジタル・ライブラリー」(竹内比呂也)
・即時オープンアクセス義務化に向けた大学図書館の現況(尾城友視・金藤伴成)
・オープンサイエンス政策をふまえた大学図書館の研究データ管理(RDM)(池内有為)
・研究データ公開支援の実際と課題-名古屋大学附属図書館の取り組み(大平司・田中幸恵)
・京都大学附属図書館、大阪大学附属図書館及び神戸大学附属図書館の連携・協力活動におけるライブラリー・スキーマ検討の取り組み(飯田智子・石黒康太・菊谷智史・坂田絵理子・田中志瑞子・西川真樹子)
・オープンサイエンス時代の大学図書館を取り巻く人事制度(ティムソン ジョウナス)
・欧米におけるオープンサイエンス時代の大学図書館員像と日本への示唆(鈴木一生)
2024年11月号 Vol.118 No.11

〇 令和6年度(第110回)全国図書館大会長崎大会への招待
・全国図書館大会の概要を全体会、15の分科会ごとに紹介
第15期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます(認定司書事業委員会)
2024年10月号 Vol.118 No.10
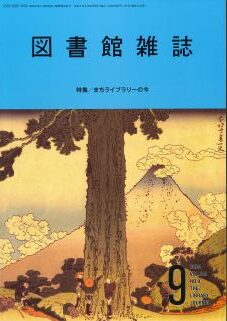
【特集】「まちライブラリーの今」
・まちライブラリーの軌跡、現況、展望と考察-個人と組織が連携した生活文化の創造(礒井純充)
・里山型まちライブラリーの模索-まちライブラリー@My Book Station茅野駅の事例(西山有子)
・本を媒介とした人の居場所-まちライブラリー@MUFG PARKからの考察(藤井由紀代)
・まちライブラリー利用者が主役になれる場-まちライブラリー@もりのみやキューズモールの事例報告(小野千佐子)
・海士町発!地域とつくる島まるごと図書館(磯谷奈緒子)
・マイクロライブラリーの受容と変遷-図書館サービス「リブライズ」12年の運営を経て(河村奨)
2022-2025年度代議員(個人会員選出及び団体会員選出)補欠選挙の公示(日本図書館協会選挙管理委員会)
2024年9月号 Vol.118 No.9
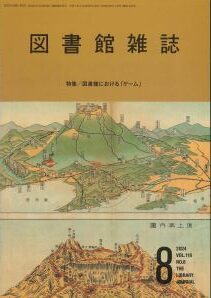
【特集】「図書館における「ゲーム」」
・本を読むということと、ゲームをするということ-インタラクティブメディアがもたらす図書館の可能性(井上奈智)
・図書館でのゲームイベントの現状と展望(高倉暁大)
・図書館・学校等向けのボードゲーム貸出について(?橋依子)
・小さな図書館ならではの試み-江津市図書館におけるボードゲーム導入のあらまし(大島久美子・佐々木有香・山?貴子)
・図書館サービスとしてのボードゲーム-図書館流通センターの取り組み ボードゲーム販売からイベント開催まで(オーレ・ベリー、尾園清香)
・公共図書館で行うTRPGの可能性-小郡市立図書館における実践例(山口茜)
・『TOSHOKAN QUEST』冒険の軌跡(近藤倫史)
・学校図書館とゲーム-ボードゲームの実践を通じた可能性の提案(杉本太志)
2024年8月号 Vol.118 No.8
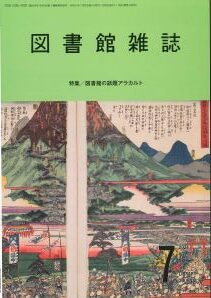
【特集】「図書館の話題アラカルト」
・カスハラ対策・感情労働者保護を目的に韓国国立中央図書館が策定した『図書館利用者対応業務マニュアル』(武田和也)
・官報電子化について-電子官報の閲覧制度と図書館との関わり(田中裕太郎)
・エフェメラと図書館-あるいは、日々は如何にして歴史のページに繰り入れられるか(北村智仁)
・デジタルアーカイブ「自由学園100年+」の構築と活用-自組織への興味を深めるツールとして(菅原然子)
・世界に一冊だけのみりょく本を創ろう!-小学生と大学生の協働・善通寺市みりょく本づくりプロジェクト(善通寺市みりょく本づくりプロジェクト実行委員会)
・「図書館に泊まろう!」実施報告-普段とは違った図書館を味わって(生武崇・齋藤森都)
・備前市「まちじゅうどこでも図書館」事業-あなたも図書館オーナーになってみませんか(小橋智裕)
・知のバトンをつなぐために-公益財団法人江北図書館の取り組み(久保寺容子)
2024年7月号 Vol.118 No.7
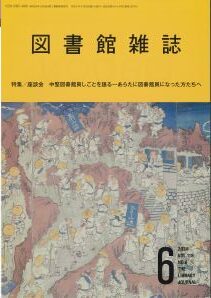
【特集】「座談会 中堅図書館員しごとを語る-あらたに図書館員になった方たちへ」(宇野亮一・小竹真鈴・小林希・田名部晃平・野中真美・松本芽生)
【報告】資料保存委員会〈資料保存セミナー〉明日からできる「資料保存の基礎技術」(JLA資料保存委員会)
2024年7月号 Vol.118 No.6
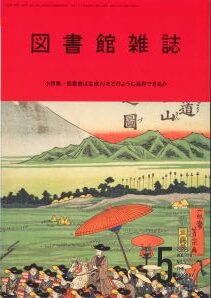
【小特集】「図書館は生成AIをどのように活用できるか」
・生成AIとは何か、図書館における協働の可能性(中島玲子)
・図書館業務での生成AI活用の可能性-図書館業務の四象限と変化へのアプローチ(高橋菜奈子)
・山中湖情報創造館における対話型AI導入について -対話型生成AIをレファレンスサービスのツールとして導入した事例の紹介
(丸山高弘・荒川知樹)
・生成AIを活用した「蔵書検索サポーター」の実証実験(吉本龍司)
2023年度大学図書館シンポジウム
「著作権法と大学図書館~令和3年の著作権法改正を中心に~」開催報告
(日本図書館協会大学図書館部会大学図書館シンポジウム担当)
第14期(2024年度)日本図書館協会認定司書名簿及び審査(報告)
(日本図書館協会認定司書事業委員会・認定司書審査会)
2024年5月号 Vol.118 No.5
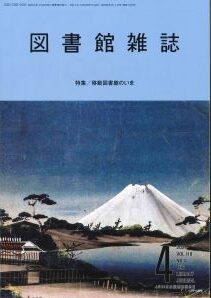
【特集】「移動図書館のいま」
・移動図書館の可能性と課題(石川敬史)
・アメリカの特徴的な取り組みに見る移動図書館の可能性
-日本とアメリカにおける移動図書館の変遷を踏まえつつ(中山愛理)
・都市計画・まちづくり分野にいる私が移動図書館に惹かれた理由(加藤浩司)
・「小さな図書館」でサービスを届ける-四万十町における移動図書館車導入事例(河野知歌子)
・製作会社の雑談(林田理花)
・子どもたちの居場所を定期的に作り続けるために-移動図書館が移動することの意味(高濱宏至)
・Book Mobile(ブック・モービル)サミット開催-移動図書館の新たな可能性を求めて(大井亜紀)
2024年4月号 Vol.118 No.4
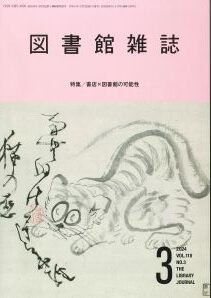
【特集】「書店×図書館の可能性」
・書店と図書館の現在地-「地域」から創造する知識基盤にむけて(柴野京子)
・「信州しおじり本の寺子屋」の取り組みと展望(上條史生)
・本にとっての“サードプレイス”-敦賀市 知育・啓発施設「ちえなみき」
(野村育弘)
・多摩市立中央図書館の開館を契機に地域の書店と「本」でつながる取り組み
(横倉妙子)
・図書館と書店をめぐって(田口幹人)
2024年3月号 Vol.118 No.3
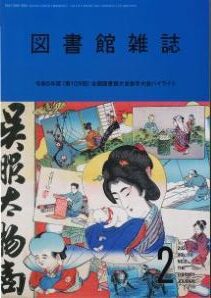
○「令和5年度(第109回)全国図書館大会岩手大会ハイライト」
・2023年11月16日(木)・17日(金)に岩手県盛岡市で開催された全国図書館大会の概要を、全体会・分科会ごとに報告するほか、大会参加者の感想を掲載。
2024年2月号 Vol.118 No.2
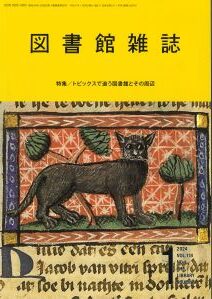
○年頭所感(植松貞夫)
○<新春エッセー>図書館は森羅万象を教えてくれる!(ずいの)
○特集「トピックスで追う図書館とその周辺」
・読書バリアフリー法に基づく横浜市の取り組みについて(神谷知栄)
・岐阜市立図書館と塩尻市立図書館の司書人事交流に期待すること(長尾勝広)
・図書館ボランティア体験を通した不登校・ひきこもり改善・自立支援(柳川涼司・腰越未樹)
・仕合わせる幸せ(長野源世)
・「健康コレクションマネジメントと健康情報の評価」研修会開催について(JLA健康情報委員会)
・今こそ漢字にふりがなを。私が考える「ふりがな再考論」-出版物およびデジタルコンテンツにルビ(ふりがな)の普及・活用を目指すルビ財団の取り組み(伊藤豊)
・インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)2023京都大会と図書館(井上靖代)
・「図書館の非正規雇用改善のための連絡会」スタート(小形亮)
2024年1月号 Vol.118 No.1
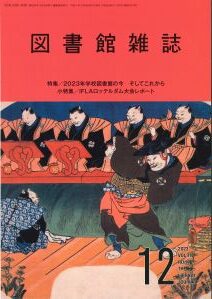
【特集】「2023年学校図書館の今 そしてこれから」
・学校図書館法70周年を懸案課題打開の起点に(塩見昇)
・学校図書館法 2014年法改正前後から現在まで(高橋恵美子)
・学校図書館におけるデジタル情報資源の活用(千田つばさ)
・令和4年度文部科学省委託事業アンケート調査から見る学校図書館と読書バリアフリーの現状と課題-読書活動へのアクセシビリティ保障(風早史子・近藤武夫)
・市町村と県による協働電子図書館「デジとしょ信州」における学校との活用連携について-リアルとデジタルのベストミックスを目指して(宮崎摩紀・宮澤優子・中村仁美・清澤千夏・小松久美・干川優)
○小特集「IFLAロッテルダム大会レポート」(三浦太郎・長塚隆・庭井史絵・高橋美貴)
2023年12月号 Vol117 No.12
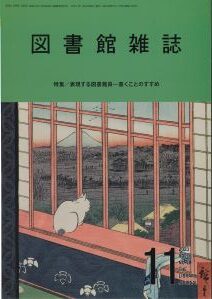
【特集】表現する図書館員-書くことのすすめ
・図書館員が執筆するということ(呑海沙織)
・現場で感じたモヤモヤを「見える化」して-認定司書オリジナル論文著作体験記(大江ひとみ)
・専門図/書館で書くということ-アジア経済研究所図書館の情報発信(坂井華奈子)
・医学図書館員として、興味を持って進めてきたこと(城山泰彦)
・「小さな気付き」を書いて残すこと(伊藤民雄)
・司書の仕事を書くこと(高田高史)
○日本図書館協会学校図書館部会第51回夏季研究集会東京大会
・学校図書館の役割を問い直す(高橋恵美子)
2023年11月号 Vol.117 No.11
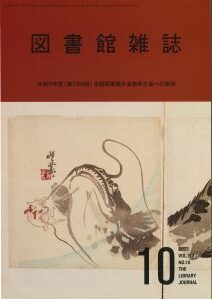
○「令和5年度(第109回)全国図書館大会岩手大会への招待」
・全国図書館大会の概要を全体会、全14の分科会ごとに紹介
○第14期「認定司書」申請(更新申請を含む)を受け付けます(認定司書事業委員会)
2023年10月号 Vol.117 No.10
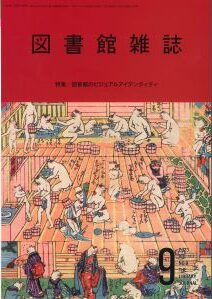
【特集】「図書館のビジュアルアイデンティティ」
・図書館におけるビジュアルアイデンティティの導入事例(近藤聡)
・図書館におけるビジュアルアイデンティティの作り方(木住野彰悟)
・太田市美術館・図書館におけるデザインのオリジナル性-綿密に設計された、永く愛されるためのビジュアルアイデンティティ(平野篤史)
・手と手を寄せ合い、重ねて、協力する施設-「tette」の愛称とロゴマークについて(小針望)
・オーテピアの開館とロゴマークの作成プロセス(高知県教育委員会事務局生涯学習課 高知市教育委員会図書館・科学館課)
・三鷹市立図書館におけるロゴマーク作成の顛末と課題(大地好行)
2023年9月号 Vol.117 No.9
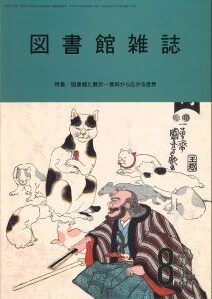
【特集】「図書館と展示-資料から広がる世界」
・資料展示会の意義-企画する側から・見学する側から(菅修一)
・「東洋一」の夢 帝国図書館展-国際子ども図書館の建物そのものを展示する(松井祐次郎)
・防災情報を伝えるため、利用者に寄り添った展示づくり-防災専門図書館の展示紹介(矢野陽子)
・図書館と司書の世界を知ってもらうための試み-文教大学越谷図書館「STARBOOKS」設置(藤倉恵一・池内有為)
・筑波大学附属図書館における電子展示のありかた(大久保明美)
・国立国会図書館における展示のデジタルシフト-「知りたい」を支援する情報発信(小川那瑠)
・周年事業における資料展示-「あれから、百年 埼玉県立図書館百周年記念資料展」を例にして(小柳直士)
・千歳市立図書館「青葉の森の水族館」展示の試み(中川伸明)
2023年8月号 Vol.117 No.8
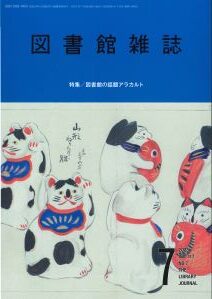
【特集】「図書館の話題アラカルト」
・国立国会図書館のオンライン資料収集制度について(平田紀子)
・公共図書館におけるシリアスボードゲームジャムの意義と可能性-くまもと森都心プラザ図書館での実践から(太田和彦)
・地域課題としての公共図書館の在り方(下吹越かおる)
・きみも大学図書館で働いてみないか-仕事の魅力を伝え、志望者のすそ野を広げるには(伊原尚子・中山貴弘・有馬良一・井上敏宏・市川鈴子)
・ポーラ文化研究所のオンラインサービス(富澤洋子)
・デジタル社会に対応した公共図書館の変革に向けて-筑波大学とつくば市立中央図書館による小中学生を対象としたブックトーク映像制作の取り組み(鈴木佳苗)
・いつも学校図書館に通う子どもがいた-学校図書館図書標準にみる格差(渡辺鋭氣)
2023年7月号 Vol.117 No.7

【特集】「既存図書館のリニューアル」
・既存図書館のリニューアルについて(中井孝幸)
・公立図書館のリニューアルと公共施設等総合管理計画(松本直樹)
・我孫子市民図書館の施設整備-長寿命化計画策定とその後の進行について(穐村喜代子)
・松阪市松阪図書館 リニューアルへの取り組み(松岡美佳)
・杉並区立中央図書館のリニューアルへの取り組み(三浦源樹)
○ユネスコ公共図書館宣言2022
(長倉美恵子・永田治樹・日本図書館協会国際交流事業委員会訳)
2023年6月号 Vol.117 No.6
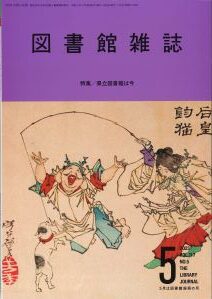
【特集】「県立図書館は今」
・特集にあたって(図書館雑誌編集委員会)
・「共知・共創の広場」を目指して-地域とともに歩む県立長野図書館の取り組み(森いづみ・小澤多美子)
・鳥取県における学校図書館支援センターの学校図書館支援(小林隆志)
・目指すべき県立図書館像-価値を創造する機能を付加する:神奈川県立図書館の事例(森谷芳浩)
・新静岡県立中央図書館の整備状況について(渡辺勝・木村雄二)
・もっと、高校図書館と連携を!-新たなサービスをいっしょに創っていこう(木下通子)
・図書館界を支えるステート・ライブラリアンたち-アメリカの図書館をつなぎ、輝かしているもの(豊田恭子)
〇第13期(2023年度)日本図書館協会認定司書名簿及び審査(報告)(日本図書館協会認定司書事業委員会・認定司書審査会)
2023年5月号 Vol.117 No.5
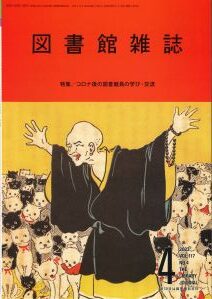
【特集】「コロナ後の図書館員の学び・交流」
・オンラインによる「中堅職員ステップアップ研修」の現状と今後について(林友幸)
・社会教育実践研究センターにおけるアフターコロナを見据えた図書館司書専門講座の運営(忰田伸一)
・大学図書館職員長期研修 オンライン開催を経て見えたもの(大和田康代・並木映李香)
・集いのなかの研鑽を続けるために-コロナ禍前後のなごやレファレンス探検隊(藤本昌一)
・最近の図書館総合展実施への取り組みを通して(長沖竜二)
○日本における大学図書館職員の意識調査 (報告)(日本図書館協会図書館調査事業委員会課題調査委員会)
○戦後図書館の草創期をいま、問う-竹内さんの新著2冊を読んで(塩見昇)
2023年4月号 Vol.117 No.4
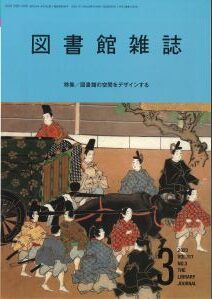
【特集】「図書館の空間をデザインする」
・図書館家具・備品の重要性と整備ポイント(柳瀬寛夫)
・図書館家具のデザイン 四つの事例(酒匂克之)
・豊かな空間を作る家具設計-明治大学和泉図書館(折戸晶子)
・神奈川県立図書館の空間づくり-新・本館における家具、書架の事例(森谷芳浩)
・「百脚繚乱」の閲覧席-石川県立図書館の家具について(嘉門佳顕・川上元美)
・大阪市立中央図書館地下1階 Hon+α!(ほな!)スペース(西尾真由子)
・菊池市中央図書館の空間デザインの取り組み(安永秀樹)
2023年3月号 Vol.117 No.3
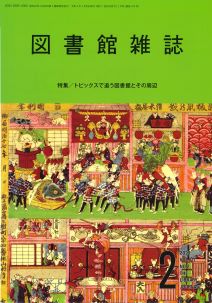
【特集】「トピックスで追う図書館とその周辺」
・創造的な学びとコミュニティが生まれる空間-県立長野図書館「モノコトベース」の取り組み(横山紗央里)
・鳥取県ライトハウス点字図書館における読書バリアフリーの取り組み(酒井詩織)
・静岡県立中央図書館における自治体資料自動収集システムの開発と今後の可能性(杉本啓輔)
・山陽小野田市における「マタニティ・ブックスタート事業」の取り組み(山本安彦)
・新聞博物館と学校図書館をつなぐ学習キット-デジタル時代に共通の言論空間つくる社会教育施設の役割(尾高泉)
・高崎商科大学図書館における「good title books@TUC図書館」の取り組みについて(高橋美樹子)
○漆原宏さんを偲んで(松島茂・庄野昭子・漆原美智子)
2023年2月号 Vol.117 No.2
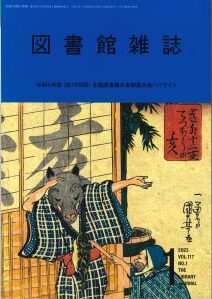
「令和4年度(第108回)全国図書館大会群馬大会ハイライト」
・10月6日(木)・7日(金)を中心にオンラインで開催された全国図書館大会の概要を全体会・分科会ごとに報告するほか、大会参加者の感想を掲載。
〇年頭所感(理事長・植松貞夫)
○<新春エッセー>
・本という窓(青木海青子)
2023年1月号 Vol.117 No.1
※2022年以前の号も順次公開いたします。

