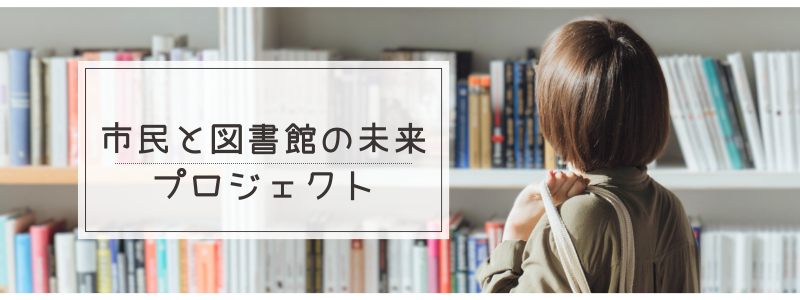
お知らせ
〇図書館総合展においてフォーラムを開催いたしました。
日時:2025年10月24日(金)10:30~12:00
会場:図書館総合展(パシフィコ横浜)第1会場(F201)
多数の方にご参加いただき誠にありがとうございました。有意義な意見交換ができたことを感謝いたします。
○フォーラムの報告を掲載しました
→2025図書館総合展「市民と図書館の未来プロジェクト」フォーラム報告
プロジェクトの開始にあたって
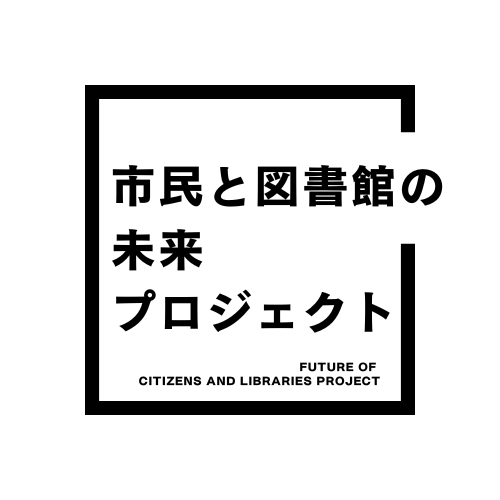
1970年に発刊された『市民の図書館』から55年の歳月が流れ,社会状況や図書館も大きな変化を遂げてきました。しかし,『市民の図書館』に掲げられたあるべき図書館像には,未完のままのものもあり,それは,現代社会においてはむしろより重視される要素を含むものもあります。
1968年から始まった「公共図書館振興プロジェクト」から57年が経過した2025年,「市民と図書館の未来プロジェクト」として現在における公共図書館の未来展望を大胆に提案していきたいと考えています。
会員のみなさま,広く市民の声も伺う機会を設けつつ,厳しい「現実」と,だからこそ掲げたい「理想」の両方に思考と対話の時間を重ねて行ければと考えています。
みなさまのご支援をどうぞよろしくお願いいたします。
市民と図書館の未来プロジェクト
主査 嶋田 学 (京都橘大学)
プロジェクトの概要
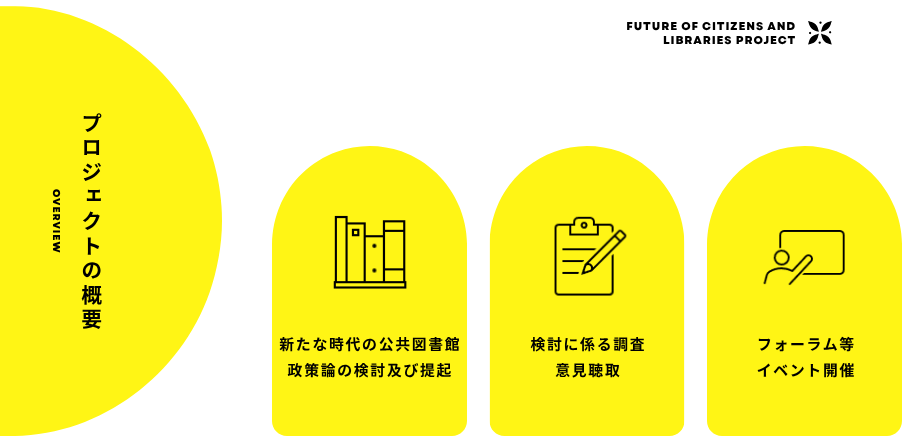
設置の趣旨
日本図書館協会は、1968年から「公共図書館振興プロジェクト」を推進し、その成果の一つとして1970年に『市民の図書館』を発刊した。同書は、戦後の公共図書館の転換となった1963年の『中小都市における公共図書館の運営』(中小レポート)、そして1965年に移動図書館車からサービスを始めた日野市立図書館の活動の躍進をベースとして、公共図書館が住民にどのようにサービスを提供すべきかを具体的に提示した。
その後、高度経済成長期の日本経済を背景とした自治体状況において始動した図書館行政は、1980年代の地方行革や1990年代の生涯学習社会への移行といった時代の変化の中においても、着実に発展を続けてきた。しかし、世紀が変わり、社会の価値観の多様化や情報環境の激変、公共政策への市場参入など、図書館を取り巻く環境は大きく変化している。
そうした中、文部科学省の図書館政策においても、2006年「これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-」が公表され、新たな時代の図書館振興のための考え方を提示し、図書館関係者には意識改革を迫っている。
21世紀の四半世紀を経た現在、『市民の図書館』とその実践が形成した公共図書館のパラダイムを客観的に認識し、時代状況に合った公共図書館政策論が求められている。
そこで日本図書館協会は、新たな時代の公共図書館政策論を模索するため、未来に向けた図書館振興プロジェクトとして、「市民と図書館の未来プロジェクト」(仮称)を立ち上げ、その活動の成果を基に新たな公共図書館政策論を提起していくこととしたい。
活動内容
本プロジェクトチームの活動内容は以下のとおりとする。
(1)新たな時代の公共図書館政策論の検討及び提起
(2)検討に係る調査、意見聴取、イベント開催等の活動
(3)その他、理事長が必要と認めた活動
組織
(1)本プロジェクトチームは、個人会員10名程度のメンバーにより構成し、理事長が指名する。
(2)プロジェクトチームには、主査を置き、理事長が指名する。
(3)活動においてはプロジェクトメンバー以外の者に協力を求めることができることとする。
設置期間及び任期
本プロジェクトチームの設置期間は、2026年3月31日までとする。メンバーの任期は設置期間と同一とする。
プロジェクトメンバー
嶋田学 京都橘大学 (主査)
高橋将人 南相馬市立中央図書館
小澤多美子 県立長野図書館 (認定司書1186)
村上さつき 松戸市立図書館 (認定司書2089)
丸山直也 山梨県立図書館
西村優子 瑞穂町図書館
是住久美子 田原市教育部次長兼図書館長 (認定司書1104)
澤谷晃子 大阪市立中央図書館(認定司書1157)
呉屋美奈子 恩納村教育委員会 文化情報センター(認定司書1194)
石川敬史 十文字学園女子大学
